| |
権力の象徴であったガラス
|
|
|
ガラスは昔から、人の心を惹きつけ、大変珍重されてきました。先日も京都府の弥生時代の墓から、美しいガラスの腕輪が発見されたばかりです。また、古代の古墳からは、見事なガラスの装飾品が多数見つかっています。古代においてガラスは権力の象徴でもあったわけです。いかにガラスのきらめきが人々の心をとりこにしてきたかがわかります。 |
|
日本最古のカットグラス |
|
日本に現存する最古のカットグラスは正倉院に収められている「白瑠璃碗」(はくるりわん)です。これはペルシアで作られ、シルクロードを経てはるばる日本まで運ばれました。しかし、日本でカットガラスが作られるようになるには、まだまだ長い年月が必要でした。
日本にガラスの製法が伝えられたのは、1559年。フランシスコザビエルよりキリスト教とともにもたらされました。 |
|
江戸時代後期に誕生 |
|
江戸時代後期の天保5年(1834)、大伝馬町(現中央区日本橋本町周辺)の加賀屋久兵衛がガラスの器の表面を金剛砂(こんごうしゃ)で削って細工をして売り出したのが最初といわれています。金剛砂というのは、紙やすり(サンドペーパー)に使われる、硬い砂のことです。加賀屋の引き札(広告)には、切子の碗や皿など、さまざまな種類のものが紹介されています。この技術は職人から職人へ脈々と伝えられました。この技術はたいへん高度なもので、浦賀に来航したペリーもその水準の高さに驚き、加賀屋がペリーに切子の花瓶を納めたという記録が残っています。 |
|
切子の基礎が確立した明治時代
|
|
明治に入って品川硝子製造所が政府によって設立され、イギリス人技師ホープトマンが招かれました。加賀屋の切子技術を受け継いでいた職人たちはここで新たに西洋の技術も学び、さらに高い技術を身につけることになります。このときに、従来の江戸切子に欧米の新しいカットデザインと技術がもたらされ、江戸切子の基礎が確立しました。当時の加工所は何人も職人を抱え、大勢の弟子が出入りする規模の大きなものでした。 |
|
クリスタルの登場 |
|
クリスタルガラスの出現は、江戸切子にとって大きな変化をもたらしました。従来のソーダ石灰ガラスとクリスタルガラスでは輝きが違います。そして、1970年代から、ガラスを削る刃が、従来の鉄の刃に替わりダイヤモンドが使われるようになりました。これにより、非常に細かくて複雑な模様が彫れるようになり、切子の表情にぐっと深みが加えられるようになりました。
伝統工芸品としての切子 昭和63年に江戸切子は東京都の伝統工芸品に指定されると同時に3名の伝統工芸士が認定され、先代根本幸雄もその一人に選ばれました。それを機に平成元年からは独創的な創作切子を募り審査する新作展が毎年開催されるようになり、現在までに7回を数えています。こうした努力により、江戸切子は伝統工芸品として広く認知されるようになりました。 |
|
江戸切子と薩摩切子 |
|
「江戸切子と薩摩切子の違いは何ですか」という質問をよく受けます。一番大きな違いは、上に被せる色ガラスの厚さでしょう。江戸は薄く、薩摩は厚いのです。
薩摩切子はもともと江戸切子がルーツです。幕末に、薩摩藩主の島津斉彬公が、薩摩の産業発展のために、ガラス製造所を薩摩にもつくりました。このとき、江戸切子の職人が呼び寄せられ、薩摩の切子づくりがスタートしました。藩の手厚い保護のもと、薩摩切子は独自の発展を遂げ、幕府献上品などに使われましたが、戦火によって製造所は焼失、斉彬公の死も重なり、薩摩切子は姿を消します。
戦後、地方意識の高まりとともに、薩摩切子復活の機運が高まり、ふたたび江戸切子職人が薩摩に招かれ、技を伝授し、薩摩切子は見事に伝統工芸美術品としての地位を回復しました。
江戸切子職人の中には、薩摩切子の製造を行い、鹿児島の業者に卸している人も数多くいます。
|
|
|
|
|
|
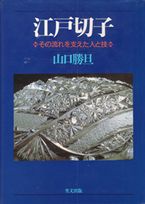
参考資料
カットガラスとその二百年にわたる業界の
歴史を知る上で不可欠な、
今は亡き山田勝旦 氏による
この 一冊。
江戸切子
里文出版 より
|





